\1000名以上が登録!ワンクリックでOK!ブロック自由!/
✅豪華特典1:正解が知りたい!負動産特化の弁護士への30分無料相談券(1万円相当)
✅豪華特典2:何千万の訴訟も!負動産の損害賠償リスク見える化シート アルファ版(1万円相当)
✅豪華特典3:最短最速!負動産放棄までの完全手順整理シート(1万円相当)
✅豪華特典4:私だけ知らない?みんなの負動産処分体験談(1万円相当)
✅豪華特典5:緊急暴露!負動産処分の裏ワザ8選(5万円相当※審査制)
✅豪華特典6:大丈夫でよかったぁ。負動産の無料診断券(1万円相当)
✅豪華特典7:いらない土地を国に返す制度の完全講義動画(全1時間30分/10万相当)
✅豪華特典8:いらない土地を国に返す制度の解説電子書籍(全88頁/5万相当)
✅豪華特典9:コピーしてすぐ役所に問い合わせ!農地情報照会テンプレート(1万円相当)
✅豪華特典10:弁護士監修!負動産処分のための土地売買契約書雛形ファイル(5万相当)
✅豪華特典11:気になる裏側「山林の引取業者に弁護士が徹底追及してみた」
✅豪華特典12:初歩から始める山林処分①最初に準備すべきこと
✅豪華特典13:初歩から始める山林処分②値が付く山ってどんな山?
✅豪華特典14:非公開情報も!負動産の最新情報配信
✅豪華特典15:負動産の有料級セミナーの無料受講の権利
※特典は予告なく終了・変更する場合があります。ご容赦ください。
※LINE登録者の方にテレビ・新聞等の取材協力をお願いする場合があります(任意)。
農地処分には相続土地国庫帰属制度がおススメ
2023年にスタートした相続土地国庫帰属制度により、不要な農地を国に返納できるようになりました。
今回は、「農地処分なら相続土地国庫帰属制度がオススメな理由」というテーマで解説したいと思います。
なお、今回のテーマは動画でも解説していますので、こちらもご覧ください。
農地は国庫帰属制度の申請実績多数――農地が4割
国によると、全国における本制度の申請件数は、8月31日までの約4か月間で885件に上っています(2023年10月4日付け法務大臣閣議後記者会見)。
その中で、田・畑が約4割を占めるとのことです。
国庫帰属制度の体験談
また、実際に農地について相続土地国庫帰属制度を申請した方の体験談を記事にしました。
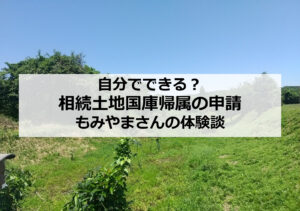
相続土地国庫帰属制度で農地を手放す場合の注意点
相続土地国庫帰属法では、国が引き取りをしない土地がブラックリスト形式で定められています。
逆に言えば、このブラックリストに該当しない土地であれば、国に引き取ってもらえるということになります。
そこで、農地がこのブラックリストに該当するかどうかを一つずつ検討していきたいと思います。
なお、結論としては、最後の要件で引っかかることが多いのが現状です。具体的には、農振農用地(青地)に該当し、地元の土地改良区(水土里ネット、みどりねっと)に水利費・賦課金などを支払っているため、国の審査が通らないというケースが多いです。
こういったケースへの対応方法を含め、当サイトでは、無料相談を受け付けています。
無料相談がきっかけで却下必至の案件が申請前に発覚したこともあります。
ただし、無料相談は予告なく終了する場合がありますのであらかじめご容赦ください。
\全国どこでも相談可能!!/
ブラックリスト①建物の存する土地
まず、「建物の存する土地」は引受の対象になりません。
もっとも、農地の場合、基本的に建物が建っていることはないと思いますので、この要件で引っかかることは少ないと思います。
ただし、農作業小屋については建物に該当する可能性が高いため、小屋の土地も併せて手放したいという場合、小屋については申請前に解体をする必要があります。
また、ビニールハウスについては、建物に該当しないと考えられますが、後述の工作物に該当する可能性があるため、こちらも撤去が必要になる可能性が高いといえます。
ブラックリスト②担保権又は使用収益権が設定されている土地
第2に「担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地」は引受の対象になりません。
農地の場合、地主さんが農業従事者に土地を貸している場合(農業従事者に賃借権という使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合)は、この要件に該当するため、そういった土地は引き取りの対象になりません。
ただし、土地を貸している場合、地代収入があり、あえて手放す必要はないでしょうし、仮に手放したいとしても土地を使っている方に安く売ればよいため、そういった場合はあえてこの制度を使う必要性がないと考えられます。
他方で、担保権が設定されている土地については、農協から借り入れを行う際に土地を担保に入れている場合に該当する可能性が高いといえます。また、借り入れをしていなくても、過去に借り入れをした際に設定した担保権の登記が残ったままという場合もあります。こういった場合も引き取りの対象にならない可能性があるため、担保権がある場合はこれを抹消する必要があります。
なお、古い担保権(休眠抵当権)については、法律上、簡易の抹消手続が用意されているため、一度、司法書士の先生に相談してみることをオススメします。
ブラックリスト③通路その他の他人による使用が予定される土地
第3に「通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地」も引き取りの対象になりません。
農地の場合、直ちにこの要件に該当しませんが、例えば、自分の農地内に農業用水路が通っている場合は、この要件に該当する可能性があります。この場合、その部分を分筆して切り離したうえで申請を行う必要があるでしょう。
ブラックリスト④土壌汚染地
第4に「土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地」についても引き取りの対象になりません。
農地の場合、土壌汚染のリスクは低いと思われますので、この要件に該当することは必ずしも多くないといえます。
他方で、農地に関しては、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」という法律があるため、後述するバスケット条項の中で、この法律に触れる土地が引き取り対象外とされる可能性はあります。
この点は今後の政省令の動向を見ていく必要があります。
ブラックリスト⑤境界不明地等
第5に「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」も引き取りの対象外となります。
農地については、境界が不明確な場合が一定数あると思われ、この点の検討を慎重に行う必要があります(具体的には公図の確認や境界標の確認等が必要になります。)。
もっとも、農地として耕されていれば、ある程度、区画がはっきりしていることも少なくないと思いますので、山林・原野ほど、この要件が問題になることはないと思います。
また、相続登記が未了の場合(先代名義のままの場合)は所有権の帰属に争いがある土地とされて、引取ができないと言われる可能性がありますので、相続登記が未了の場合は、相続登記を終えてから申請を行う必要があります。
ブラックリスト⑥崖地
第6に、「崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの」が引取の対象外となります。
農地が崖地になっていることは必ずしも多くないと思いますが、棚田や茶畑等、斜面に農地がある場合もあるため、こういった場合は、この要件に引っかからないか注意する必要があります(具体的な基準は政令に定められる予定です。)。
ブラックリスト⑦残置物がある土地
第7に「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」も引き受けの対象外です。
田んぼや畑などの場合、作物等が刈り取られていれば、基本的にこの要件を満たすことはないと思われます。
他方で、果樹園のように木が沢山植えられている場合、この要件に該当する可能性があります。
山林に生えている木のように、特別の管理を要しない樹木であれば、この要件に引っかからない=通常の管理・処分を阻害する樹木にはならないと考えられますが、果樹の場合、手入れが大変ですので、この要件に該当する可能性が相対的に高いと考えられます。
法務省の考え方は、まだ不透明ですが、果樹園の場合は、樹木の除去が必要になる可能性があります。
また、ビニールハウスがある場合も、この要件に引っかかる可能性が高いと思われますので、制度を利用する際はビニールハウスの撤去が必要になる可能性があります。
ブラックリスト⑧地下埋設物がある土地
第8に「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」についても引き受けの対象外となります。
農地に地下埋設物が埋まっていることは基本的に考えられないと思いますが、申請を検討する前に、埋蔵文化財包蔵地に該当しないか、念の為、行政に確認しておくことがよいと思います。万が一、埋蔵文化財包蔵地に該当すると、この要件に引っかかる可能性があります。
ブラックリスト⑨係争地
第9に「隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの」も引き受けの対象外です。
農地だから当然に係争地に該当するという要素はないと思いますが、例えば、農地の貸付期間が終わっているが、事実上返還されないなどのトラブルがある場合は、そのトラブルを解消してから申請する必要がありそうです。
ブラックリスト⑩その他
最後に、「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの」も引き取りの対象外です。
農地との関係でいうと、以下のように非常に難解な要件が定められています。
四 法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地
五 法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの
結論としては、土地改良区という団体に賦課金(水利費等)という名目で支払が発生している土地は引取の対象外ということです。
現状、この要件で引っかかる土地が多いのが実情です。
具体的には、農振農用地(青地)に該当し、地元の土地改良区(水土里ネット、みどりねっと)に水利費・賦課金などを支払っているというケースが少なくありません。
逆に言えば、このような賦課金がない農地(例:第二種農地等)であれば、要件を満たす場合が十分にあります。
負担金
以上のブラックリストに該当せず、国庫帰属が認められる場合でも、申請者は負担金を支払う必要があります。
この負担金は、「国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭」のことをいいます。
農地の場合、面積が大きくなると、管理費用も大きくなる可能性があります。そのため、面積の大小によっては、負担金が高額になり、事実上手放すことができないという可能性もあります。
具体的には、市街地の農地、農振農用地(青地)、土地改良区内の農地については、面積に応じて負担金が高額になるケースもあります。
さいごに
いかがでしたか?今回は、相続土地国庫帰属制度で農地を手放すことができるか?を解説しました。
もし、この記事が「わかりやすい」「勉強になった」と思った方はSNS等で共有していただけると大変うれしいです。
なお、LINEでお友達登録をしていただくと、最新のお役立情報を受け取ることができます。
\1000名以上が登録!ワンクリックでOK!ブロック自由!/
✅特典1:あなたの負動産は大丈夫?負動産リスク診断シート アルファ版(5千円相当)
✅特典2:やるべきことが分かる!負動産処分の課題整理シート(5千円相当)
✅特典3:事例集「私の負動産処分体験談」(1万円相当)
✅特典4:講義動画「負動産処分の裏ワザ8選」(5万円相当※審査制)
✅特典5:負動産の無料診断券(1万円相当)
✅特典6:国庫帰属制度の講義動画(全1時間30分/10万相当)
✅特典7:国庫帰属制度の電子書籍(全88頁/5万相当)
✅特典8:すぐに使える!農地情報照会テンプレート(1万円相当)
✅特典9:負動産処分のための土地売買契約書雛形ファイル(5万相当)
✅特典10:限定記事「山林の引取業者に弁護士が徹底追及してみた」
✅特典11:講義動画「山林を賢く手放す方法①最初に準備すべきこと」
✅特典12:講義動画「山林を賢く手放す方法②値が付く山ってどんな山?」
✅特典13:負動産や相続土地国庫帰属制度の最新情報配信
✅特典14:負動産処分の有料級セミナーの無料受講の権利
✅特典15:チャット(LINE)による個別無料相談(無制限)
※特典は予告なく終了・変更する場合があります。ご容赦ください。
※LINE登録者の方にテレビ・新聞等の取材協力をお願いする場合があります(任意)。
また、期間限定で弁護士による無料相談を受け付けています。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
電話から
こちらの番号にお電話いただき、「使わない土地の無料相談がしたい」とお申し付けください。
027-212-8592
※月~金 10:00-17:00まで(不在時は折り返します)
LINEから
こちらからお友達登録いただき、「無料相談がしたい」とお申し付けください。


