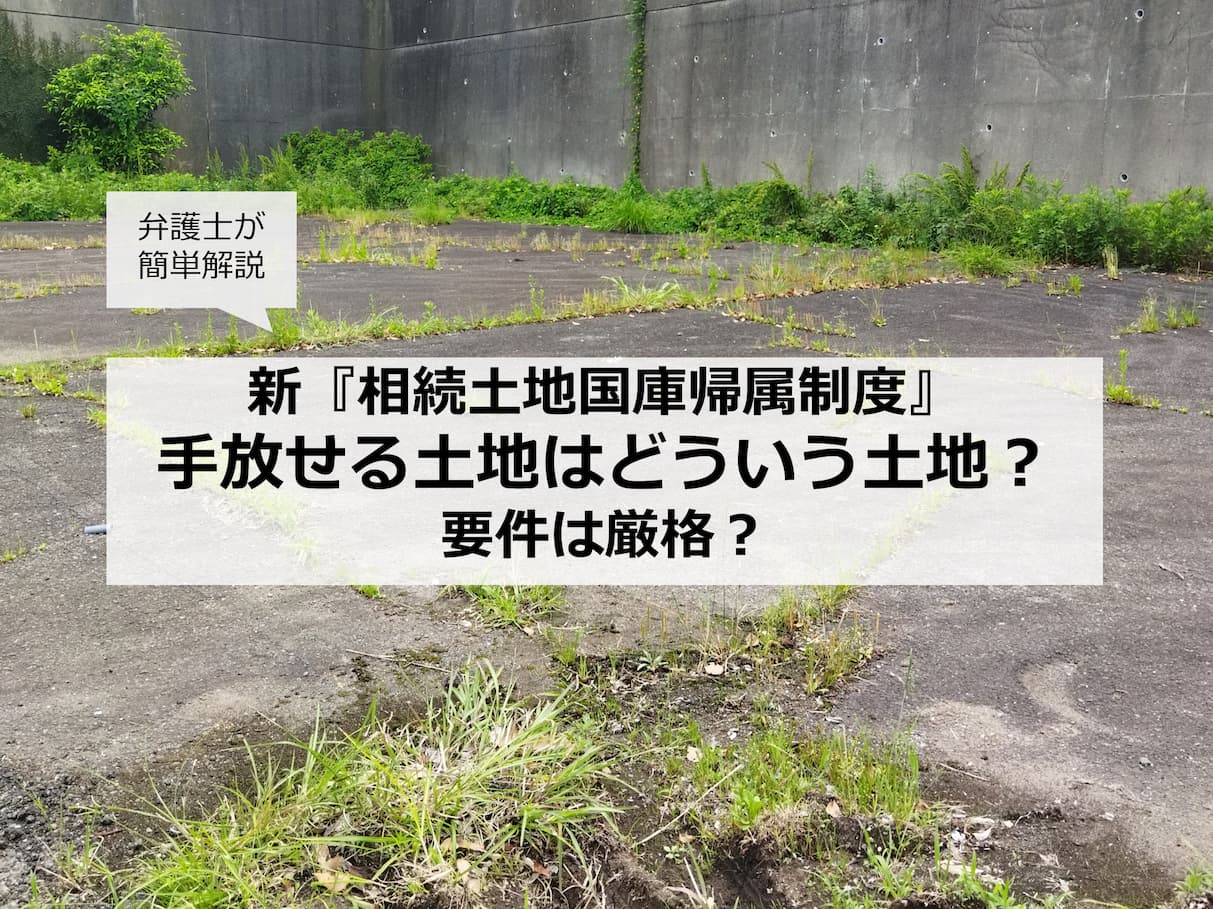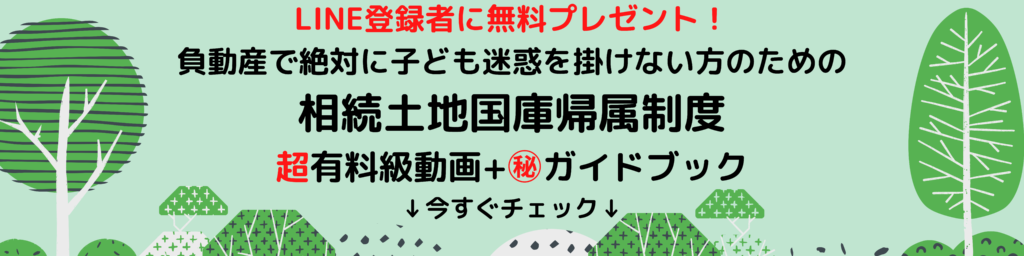
\ワンクリックでOK!解約自由!有料級情報満載/
引取不可のブラックリストがある!
国は、相続土地国庫帰属法のブラックリストに該当する土地を引取りません。
このブラックリストには、次の2種類があります。
- 申請すらできない土地のリスト(門前払いとなるもの)
- 申請はできるけど、状況によって手放すことができない土地
それぞれ詳細を見ていきましょう。
ブラックリスト一覧
申請すらできない土地(門前払いとなるもの)
- 建物がある土地(更地じゃないとダメ!)
- 担保権(例:抵当権)や賃借権等がある土地
- 地元住民等が利用する土地(通路、墓地、境内地、水路等)
- 土壌汚染地
- 境界不明地・相続未登記地等の権利関係が曖昧な土地
申請はできるけど、状況によって手放すことができない土地
- 管理困難な崖地
- 管理処分困難な残置物(例:放置自動車、樹木等)がある土地
- 管理処分困難な埋設物(例:埋蔵文化財、ガラ、廃棄物)がある土地
- 公道までの通路がない土地等
- その他(災害・獣害危険区域、賦課金が必要な土地改良区等)
申請すらできない土地(門前払いとなるもの)
建物がある土地
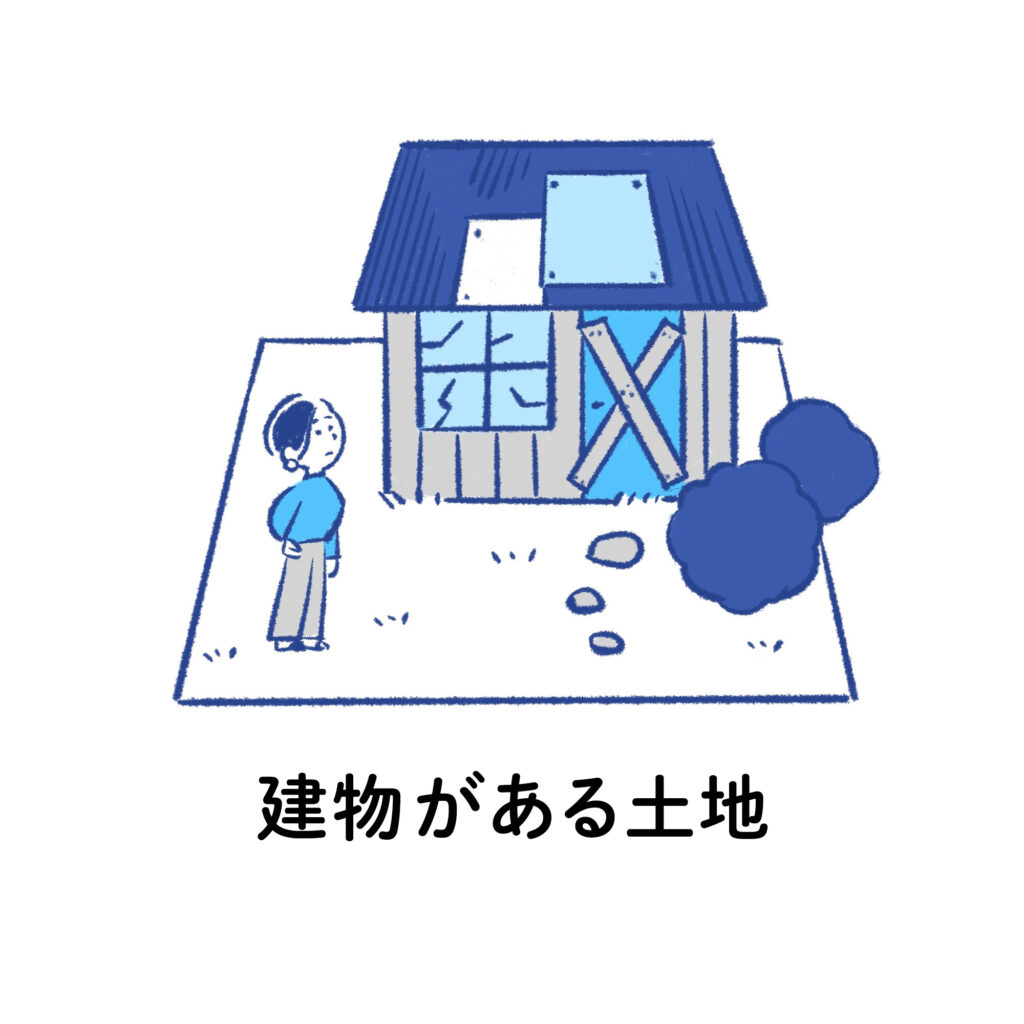
まず、建物がある土地は申請ができないとされています。
そのため、建物は取り壊した上で承認申請をしなければなりません。
もっとも、取壊しには相当の注意を払ってください。
なぜなら、それがどんなボロ物件でも建物があれば、引き取ってくれる方が見つかる場合があるからです。
建物があるとダメな理由
建物は、一般に管理コストが土地以上に高額です。
老朽化すると、管理に要する費用や労力が更に増加するだけでなく、最終的には建替えや取壊しが必要になります。
このように建物は通常の管理・処分に多大な費用・労力を要することが明らかです。
そのため、建物が存在する土地は、承認申請をすることができません。
なお、山のような広大な土地の一部に建物が存在する場合であっても申請はできません。
少し厳しすぎる気もしますが、この場合、建物の解体が必要になります。
どこからが「建物」?
そもそも「建物」かどうかは、どう判断すればよいでしょうか。
結論としては、現地の建築物に対応する建物登記があれば、それは建物と判断されます。
ただし、建物の登記がされていなくても、建築物に、屋根や周壁などがあり、土地に定着している場合、それが利用可能な状態にあれば、建物といえます。
もちろん、建物かどうかが微妙なものもあるでしょう。
しかし、その場合も、工作物として扱われ、後で説明する要件に引っかかる場合があります。
建物の”登記だけ”が残っている場合
建物は解体済みなのに登記だけ残っているということがあります。
この場合、滅失登記という手続が必要です。
もっとも、滅失登記が未了でも、相続土地国庫帰属制度の申請は却下されません。
ただし、滅失登記自体は義務ですので、すみやかに行うことが望ましいです。
担保権や使用収益権が設定されている土地

次に、担保権や使用収益権が設定されている土地も引き取りの対象外です。
使用収益権というと、賃借権、地上権、地役権、入会権、森林経営管理法の経営管理権等があります。
例えば、農地の場合、地元の農家さんに貸していることがあると思います。
この場合等は賃借権が設定されているということになります。
登記がなくてもバレますので気を付けてください。
なお、賃借権が設定されている場合でも、登記がされていないケースが結構あります。
登記されていないからバレないだろうと考えるのは早計です。
法務局で農業委員会に照会を掛けますので早々に分かります。
申請する場合は、農地を返してもらってから申請してください。
また、近隣住民や隣接地所有者へのヒアリングで判明する場合もあります。
例えば、「あの土地は、●●さんが耕作しとるよ」等の形で情報提供がされる可能性があります。
この場合は、申請者から賃借権等がないことを証明する書類(上申書)を提出する必要があります。
土地内に電柱・電線がある場合
また、土地内に電柱があったり、土地の上空や地中に電線が通っていることがあります。
この場合、法的には、賃借権や地役権という権利が設定されていることがあります。
もっとも、法務省によると、自治体等が電柱やマンホールを設置するために、土地のごく一部に利用権を設定している場合、「使用収益権」に該当しないこととされています。
ただし、土地の利用を妨害する物が置いてあると別の要件に引っかかる可能性はあるため、その点は要注意です。
担保権が設定されている場合
担保権というと、抵当権、質権、先取特権等があります。
また、いわゆる譲渡担保権(所有権を担保目的で移すもの)についても、担保権に該当します。
なお、登記がされているか否かにかかわらず、これらの権利が設定されていることが発覚した場合は引き取りの対象外になります。
ご相談でよく見るのが、明治時代や大正時代に設定された抵当権が残っているケースです。
このような場合、債務がすでに完済されていたり、消滅時効が完成していたりすることがあります。
そのため、現実的には、抵当権が行使される可能性は低いです。
もっとも、相続土地国庫帰属制度では、抵当権の登記がある場合は承認申請をすることができません。
そのため、古い抵当権が残っている場合は、専門家(司法書士等)に依頼して登記を抹消してもらう必要があります。
その他(買戻特約、差押登記、仮処分の登記)
このほかにも、買戻特約、差押登記、仮処分の登記、譲渡担保権の登記等が残っていることがあります。
こういった登記がある場合も申請が却下されるため、登記簿を見て該当するものがないかをチェックすることが必要です。
地元の住民等が利用する土地(通路、墓地、水路、境内地等)

次に、地元住民の方などが利用する土地も引取り不可とされます。
このような土地を国が引き取ると、その管理に当たって使用者等との調整が必要であるなど、通常の管理・処分に多大な費用・労力を要するが明らかだからです。
「他人による使用が予定される土地」の具体例としては、以下の土地があります。
- 道路法上の道路など法令により他人による使用が予定される土地
- 現に通路として利用されている土地
- 墓地
- 境内地(けいだいち※ざっくりいうとお寺の土地等)
- 水道用地、用悪水路又はため池として現在使用されている土地
それぞれ見ていきましょう。
通路※最も問題になりやすい
まず、このなかで最も問題になりやすいのが、現に通路として利用されている土地です。
特に、別荘地や宅地などを所有している方は、要注意です。
なぜなら、宅地と一緒に隣接する道を所有していることがあるからです。
この場合、その隣接する道が、この要件に該当する可能性があります。
なお、登記簿で「公衆用道路」とされている土地があります。
もっとも、このような土地でも、現在、通路や道路として使用されていない場合は申請は却下されません。
原野商法で騙されて買った土地や限界ニュータウンのような地域では、公図上、道があっても、現地は道として利用されていないというケースもあります。
ただし、通路として利用されていない場合でも、「共有」になっているときは要注意です。
この場合、共有者全員で申請する必要があります。
ご懸念がある場合は、登記簿を確認して共有になっていないか確認してみましょう。
山林の場合、林道や登山道が通っていることがあります。
これらも実際に利用されている場合は、「通路」に該当し、却下される可能性があります。
もっとも、作業道や管理歩道などは、土地の管理に必要な道ですので、通路には該当しません。
水路
なお、水路についても、水路して現在使用されていない場合は申請が可能です。
墓地
墓地については、土地の一角に墓石がある場合等は却下されます。
登記簿の地目欄で「墓地」となっていて、現地に墓石があることもあります。
これらの場合、都道府県に墓地としての登録を確認してみましょう。
仮に登録がある場合は、墓地の廃止の手続を行い、墓石も撤去する必要があります。
廃止の手続をしても、墓石が残っていると、却下される可能性があるため、注意してください。
なお、土地を分筆し、墓地の部分を除いた土地について承認申請をすることは可能です。
ただし、墓地だけ残っても目的が達成できないという方も少なくないでしょう。
境内地
同様に、境内地についても地目上、境内地となっていれば、要注意です。
ただし、実際に境内地として利用されていなければ、却下はされません。
逆に、地目が境内地になっていなくても、実際に境内地として利用されている場合は却下される可能性があります。
この要件については、次の記事でも詳細を解説しています。
>【速報】原則20万で土地を国に?相続土地国庫帰属法政令公表!【弁護士が徹底解説】
土壌汚染されている土地

次に、土壌汚染されている土地についても引き取りが認められません。
具体的な基準は、土壌汚染対策法における環境省令で定める基準と同じです。
もっとも、すべての事案で、土壌汚染がないことを調査したり、証明する必要はありません。
法務局の方でも、現地で土を掘り返して調査することも想定されていません。
法務局の方で、申請者や自治体等へのヒアリング等で申請地の過去の用途(例:過去に工場があった等)を確認します。
そのうえで、例えば、土壌汚染対策法6条の「要措置区域」や同法11条の「形質変更時要届出区域」に存在する土地である場合があります。
また、現地で土地の変色や異臭等があり、明らかな異常が認められる場合もあり得ます。
こういった場合は、土壌汚染の可能性があるため、申請者に確認が入ります。
そこでの弁明がうまくいかないと、土壌汚染調査が求められることがあります。
この土壌汚染の調査を拒否すると、申請が却下される可能性が出てきます。
ただし、工場跡地等のように土壌汚染が疑われるケース以外は、土壌汚染の調査が必要なケースは少ないと考えられます。
なお、近いものとして、放射性物質が存在する土地、避難指示区域内の土地、ダイオキシンなど、特定有害物質ではないものの人体に有害と思われる物質が存在する土地等があります。
もっとも、これらに該当することをもって直ちに却下されるわけではありません。
境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

「境界が明らかでない土地」についても引取の対象外です。
典型的には隣地所有者との間で境界の認識が一致しない場合が挙げられます。
また、申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地についても引取の対象外です。
他にも、図面と現地の状況が大幅に食い違う場合や現地で境界点が確認できない場合も引取対象外です。
こういった土地は、国が管理するうえで支障が生じることが明らかですので、引き取りの対象外とされました。
この要件については、多くの法律専門家が「厳しい条件だ」といいます。
とりわけ、山林では、境界がわからないことが多いため、このように言われることが多いです。
しかし、詳細に見ていくと必ずしも厳しいものではありません。
この点は、審査の流れを見ると分かります。
相続土地国庫帰属制度における境界の判断方法
相続土地国庫帰属制度における境界は、主に次の2つ点から判断されます。
- 提出した図面・写真と現地にズレがないか?
- お隣さんから、異議が出ないか?
①提出した図面・写真と現地にズレがないか?については、現地に境界標と一致している必要があります。
境界標がない場合、境界点を明らかにする目印を立てる必要があります。
紅白ポール、プレートなどの設置で差し支えありませんが、一時的なものではだめです。
申請の審査時及び国庫帰属時(承認時)にも判別することができるよう、固定的なものである必要があります。

(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」より)
また、誤解されやすいのですが、隣の土地の所有者と境界について合意した書面(境界確定書等)や境界確定図(測量図)を提出する必要はありません。
ただし、境界確認書等を保有している場合は、申請時に写しを添付することが推奨されています。
②お隣さんから、異議が出ないか?については、法務局からお隣さん(共有地の場合は共有者全員)に手紙を出すことで確認します。
回答期限は2週間です(海外の場合は4週間)。
2週間経っても、返信がない場合、再度、通知をします。
この回答期限も2週間です。
結局、回答がなかった場合は、異議なしとして審査が進められます。
(ただし、現地調査の際に近隣住民から異議が出た場合は、追加の対応が必要になる可能性があります。)
なお、法務局からお隣さんにお手紙を送付する際、申請時に提出した図面が同封されます。
そのため、申請前に、お隣さんに手紙を送っておくとスムーズに進みます。
もし、お隣さんから異議が出た場合はどうなるでしょうか?
この場合、直ちに却下になりません。
お隣さんと調整し、争いがなくなった場合は、引き続き審査が進みます。
ただし、猶予期間は2か月です。
遠方で調整に時間が掛かる可能性がある場合は、申請前にお手紙を出しておくことがよいでしょう。
なお、お隣さんが住所変更登記等をしていないため、お手紙が届かない場合があります。
このような場合、法務局の方で追加の調査をすることはありません。
異議なしと判断されて、審査が先に進みます。
この辺は非常に重要な論点ですが、内容も難しいため、境界のことがよくわからないという方は無料相談をお申し込みください。
ただし、無料相談は予告なく終了することがあります。あらかじめご容赦ください。
\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/
なお、誤解されやすいのですが、いわゆる筆界未定土地又は地図がない土地でも申請が認められる可能性はあります。
あくまでも、申請者から土地の範囲が明確に示され、その土地の範囲について隣地所有者と認識が一致していれば争いがないものと判断することになります。
そのため、筆界未定又は地図がないことのみをもって、境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地として承認申請を直ちに却下することにはなりません。
また、法務局で発行してもらえる公図や地積測量図とズレがあっても直ちに却下されるわけではありません。
申請はできるけど、状況によって手放すことができない土地
一定の勾配・高さの崖があって、管理に多大な費用・労力がかかる土地

次に、崖地がある場合、状況によって引き取りが認められないことになっています。
具体的には、勾配が30度以上で高さが5メートル以上の崖であって、崩落の危険性があると考えられる場合、引き取ることはできません。
なお、崖地の基準は政令で定められているのですが、こちらについては次の記事をご覧ください。
>【速報】原則20万で土地を国に?相続土地国庫帰属法政令公表!【弁護士が徹底解説】
崖がある土地は、安全対策等の管理コストがかさむおそれが類型的に高く、これを国庫に帰属させることは財政負担の観点から相当でないからです。
他方で、例えば、周囲に人家が存在せず、天災等により崖崩れが発生したとしても周囲の土地の損害発生の可能性が低いような土地については、引取の対象になりえます。
また、隣の土地に危険な崖がある場合でも、申請をする土地に危険な崖がなければ、その他の要件に該当しない場合は引き取ることは可能と考えられます。
ちなみに、もし国が引き取りを拒否した場合でも、危険な崖については、急傾斜地法等で行政が対応することがありますので、必要に応じて行政にも相談してみてください。
土地の管理・処分を阻害する有体物(例:放置自動車、樹木等)が地上にある土地

土地上に残置物がある場合も、状況によって引き取りの対象外です。
以下のようなものが考えられます。
- 果樹園の樹木
- 民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木の恐れがある枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木
- 放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹
- 過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
- 建物には該当しない廃屋
- 放置車両
例えば、果樹園の樹木については、一般的に、放置しておくと鳥や獣や病害虫の被害の要因となる関係で、定期的に枝の剪定や農薬の散布などの作業が必要になるため、こういった土地は引取の対象外になる可能性が高いといえます。
他方で、森林において樹木があるのはむしろ通常ですので、安全性に問題のない土留めや柵がある場合などには、引取が認められることがあります。
また、樹木自体は切られているものの切り株が残っている場合は、基本的には残置物に該当しないと考えられます。
さらに、電柱は、管理又は処分をするに当たり過分な費用を要する工作物に該当しないと思われますが、電力会社の地役権等が設定されている可能性があるため、その場合は、引取不可となります。
土地の管理・処分のために除去しなければいけない地下埋設物(例:埋蔵文化財)がある土地

地下にいわゆる埋設物等の有体物がある土地についても、状況次第で引取不可になります。
具体例として次のようなものがあります。
- 管理を阻害する産業廃棄物や屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)
- 地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
- 現在使用されていない古い水道管、浄化槽、井戸
- 大きな石
こういった土地は、その管理・処分に制約が生じ、その撤去のために多大な費用がかかる上に、場合によっては周囲に害悪を発生させるおそれがあるためです。
なお、③については、現在も使用が可能な水道管やガス管などの一般的なものは、該当しない可能性があります。
また、埋設物の有無の判断方法ですが、申請地の過去の用途の履歴について、申請者の認識や地方公共団体が保有している情報等を調査することにより、判断することが想定されています。
そのうえで、埋設物の可能性がある場合は、申請の際にボーリング調査が求められることになります。
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

隣地所有者等との問題を解決しなければ利用できない土地も引取りの対象外です。
具体的には2つの類型があります。
- 公道までの通路がなく、かつ、実際に公道に出られない土地
- ①以外で所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く)
こういった土地は、管理を行う上で障害が生ずるおそれが高いからです。
②の具体例としては次の3つがあります。
- 所有者以外の第三者に不法に占有されている土地
- 隣接地から継続的に流水がある土地
- 管理費の支払を巡ってトラブルになるような別荘地
以上については、相続土地国庫帰属法施行令で定められているのですが、この政令については次の記事をご覧ください。
>【速報】原則20万で土地を国に?相続土地国庫帰属法政令公表!【弁護士が徹底解説】
その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
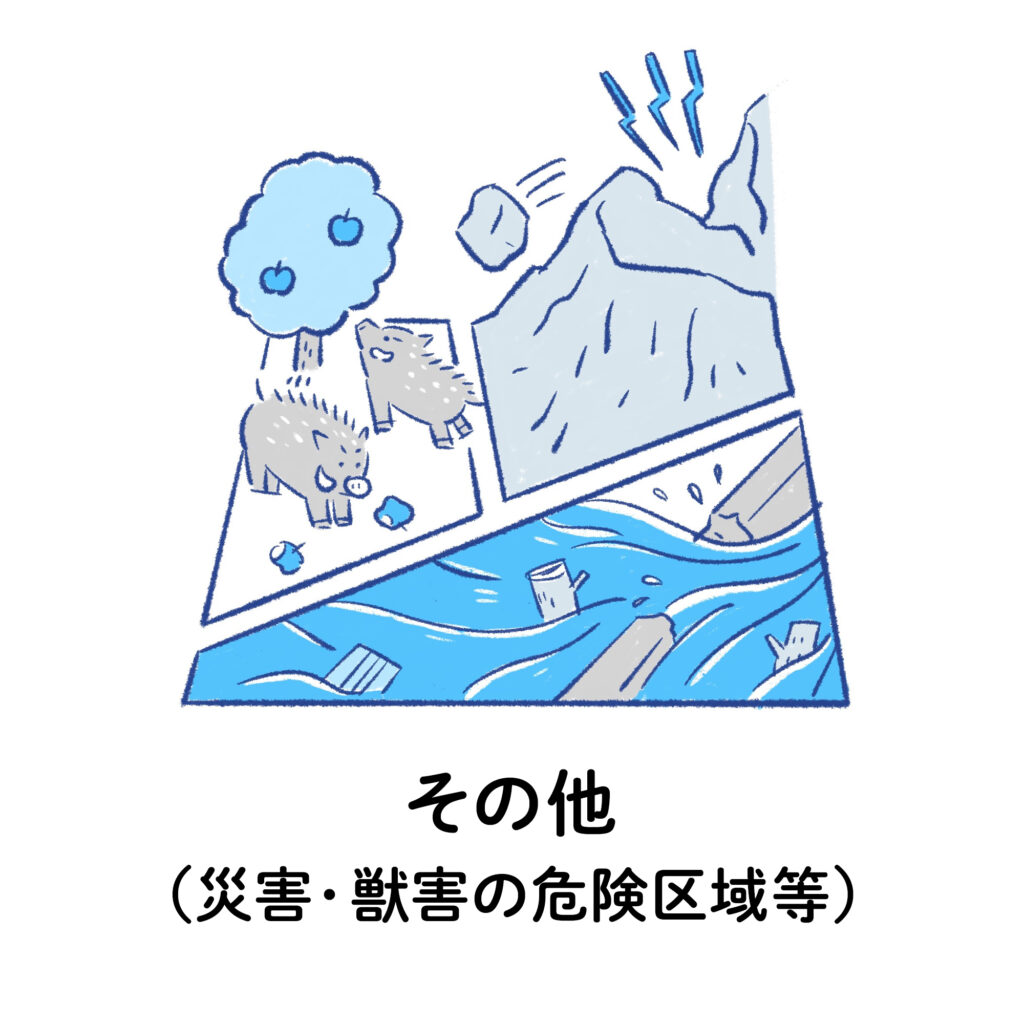
最後に、その他として次のような土地が引取りの対象外とされています。
- 土砂崩落、地割れなどに起因する災害により、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命、身体又は財産に対する被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く。)
- 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く。)
- 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備を要する森林(軽微なものを除く。)
- 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
- 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
①については、例えば、土砂の崩壊の危険のある土地について崩壊を防ぐために保護工事を行う必要がある場合、大きな陥没がある土地について人の落下を防ぐためにこれを埋め立てる必要がある場合、大量の水が漏出している土地について排水ポンプを設置して水を排出する必要がある場合、などが考えられます。
②については、例えば、生息する動物(スズメバチなど)や病害虫を駆除する必要がある土地です。
その際、(a)主に農用地として利用されている土地であればその周辺の地域における農用地の営農条件に著しい支障が現に生じているかどうかについて、(b)主に森林として利用されている土地であれば森林病害虫等の発生により駆除やまん延防止のため措置を現に必要としているかどうかについて確認します。
生息する動物の危険性が低い、又は危険であっても生息する数が極めて少ないなどの理由により、被害の程度や被害が生ずるおそれの程度が軽微であるような場合は、引き取ることができます。
また、イノシシやクマなどが生息している土地については、具体的に人などに被害が生ずる可能性が高い場合は引き取ることができず、抽象的な可能性にとどまる場合には、引き取ることができます。
③に関して、(a)人工林については、適切な間伐等が実施されているかどうかを、(b)天然林については、標準伐期齢に達しているかどうかを確認します。
④⑤については、例えば、土地改良法第36条第1項の規定により賦課徴収される金銭(土地改良事業で整備される水利施設等の建設費用、当該事業で整備された水利施設等の利用や維持管理に係る経常的経費)が考えられます。
なお、金額にかかわらず賦課金が発生している場合には、土地を引き取ることはできません。
逆に、金銭債務を消滅させた場合は可能です。ただし、国の審査が完了する前に金銭債務を消滅させる必要があります。
以上については、相続土地国庫帰属法施行令で定められているのですが、この政令については次の記事をご覧ください。
>【速報】原則20万で土地を国に?相続土地国庫帰属法政令公表!【弁護士が徹底解説】
最後に
なお、この制度の全体像については、次の記事で解説していますので興味がある方はぜひご覧ください。
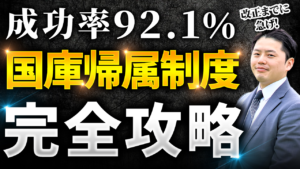
お知らせ
お友達登録で限定情報を取得
当サイトのLINE公式アカウントにご登録いただくと最新情報・限定情報がもらえます。見落としたくない方はご登録をお願いします。また、弁護士への無料相談に申込むこともできます。ただし、無料相談は予告なく終了することがあります。

\ワンクリックで簡単!解約自由/
LINE無料相談
なお、弁護士に相談したいけど、弁護士事務所に出向いて相談するのは緊張する…。
そんな方のために、弁護士がLINEによる無料相談を受け付けています(初回30分無料)。
ご相談はこの記事の内容以外のことでも大丈夫です!
ただし、無料相談は予告なく終了することがあります。
\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/
専用フォームから問い合わせ
電話相談
なお、こちらの番号にお電話いただき、「使わない土地の相談がしたい」とお申し付けいただければ、電話による相談も可能です。なお、無料で対応できない場合もありますのでご容赦ください。
※月~金 10:00-17:00まで(不在時は折り返します)
弁護士 荒井達也
群馬弁護士会所属。負動産問題に注力する弁護士。読売新聞などの全国紙からの取材対応や専門書の出版等を通じて相続土地国庫帰属制度や負動産の処分方法を解説している。
詳細はこちら→プロフィール詳細

参考文献
法務省民事局「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
法務省民事局「相続土地国庫帰属制度について」
村松秀樹他「Q&A令和3年改正民法 改正不登法 相続土地国庫帰属法」(きんざい